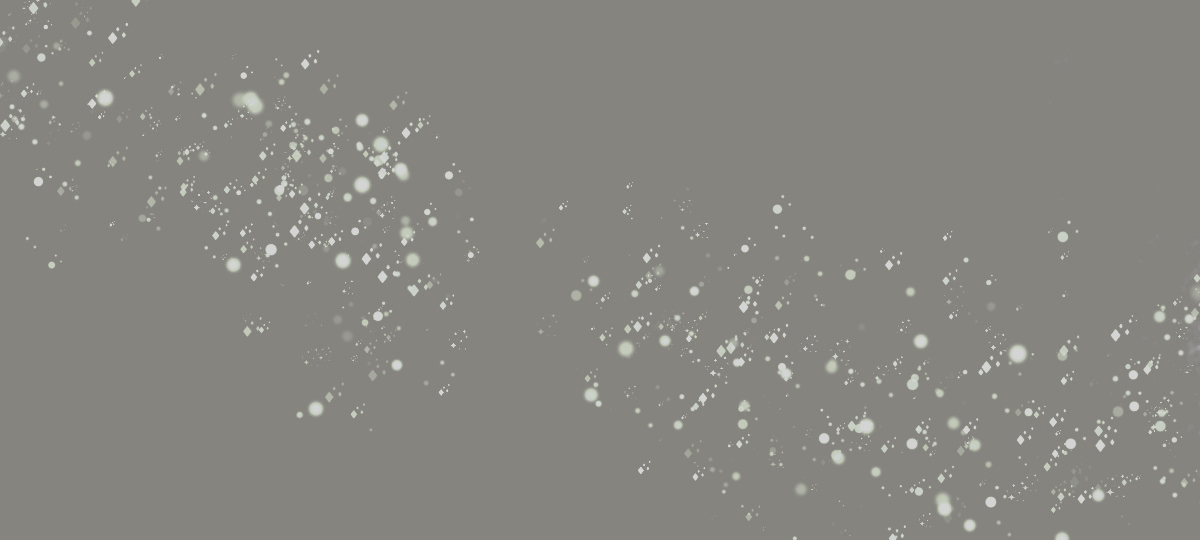夜空の星を眺めていた。
人間界の山の麓にある小さな集落。数軒の家に家畜小屋と畑しかないような場所だ。街灯といったものもほとんど無く、夜にはすっかり闇に包まれる。普段は牧草畑として利用されているその場所はすっかり雪に覆われて、きらきらと月の光を浴びながら辺りを青白く照らしていた。
雪で覆われた世界は静寂だ。虫や動物の声もしない。そんな静かな世界の中心で軀は一人寝転び夜空を眺めていた。
冬は空気が澄む。星達が一際煌めいて見えて、いつまで見ていても飽きない。
(このまま吸い込まれそうだ……)
そんな事を思ってしまうほどの星空がそこにはあった。
魔界では月は見えるが星というものは見えない。そもそも月といっても魔界と人間界のそれは違う。
魔界の月には実体がないのだ。何層にも次元の階層がある魔界にとって空は幻でしかない。場所によっては月すら見えない層もある。一説にはその昔人間界で月を見て感動した妖怪が魔界に似せたものを作ったなんて話もあるくらいで、実際見えている月がなんなのかも未だよく分かっていない。
空の境は次元の境。
人間界のように高い空は無いのだ。今まではそんな事を気にした事も無かった軀だったがここ数十年、人間界を行き来するようになり魔界の空を窮屈に感じるようにもなった。
箱にぎゅうぎゅうに詰められたような世界。
そんな世界で長い時間生きる事はどういう理なのか。
息を思いきり吸い込めば、ひんやりとした冷たい空気が胸を満たす。もっともっと満たしたら何かが変わるんじゃないだろうか。
もっともっと息を吸ったら──
星空の下、軀はそっと瞳を閉じた。
*
パタパタとはためく白を軀はぼんやりと眺めていた。今日は冬にしては暖かい日らしい。雪菜が嬉しそうに洗濯物を干している。
雪菜の足元では猫が二匹甘えるように鳴いている。もう少し待っていてくださいねと雪菜は猫に話しかけながら洗濯物を次々と干していく。少し冷たい乾いた風が吹けば、干されたシャツやタオルが風に揺れる。
「軀さん、洗濯物を干し終えたらお茶にしましょう。もう少し待っててくださいね」
さきほどの猫達と同じように話しかけられて、軀は思わずくすりと笑う。分かったと返事がわりに庭にいる雪菜に向かって手を振った。
「やっと笑ってくれましたね」
ティーポットのお茶をカップに注ぎながら雪菜が軀に話しかける。
「そうだったか?」
「えぇ、ずっと昨日から難しい顔をされてましたよ。また兄が何かしたのかと心配していました」
ふらっと人間界にやってくる軀は良く雪菜のところに顔をだす。ここだと飛影が早々にやって来ないという理由もあるが、何より雪菜の側が心地よいからだ。根掘り葉掘り問い詰めてくるような事もなく、程よいタイミングで話を聞いてくれる。他愛もない話をして、魔界では珍しい人間界の食べ物を食べてお茶を飲んで一息つく。魔界とはまるで違うその場所は軀の大切な場所になりつつあった。
「手合わせ手合わせ言うから少し逃げてきただけだ。最近のアイツの成長は目覚ましいからな。オレが相手しなくても勝手に強くなるだろ」
「兄は早く軀さんより強くなりたいんですよ。それに素直じゃないから……」
クスクスと笑いながら話す雪菜を見て、軀は少し照れたようにカップのお茶に口をつけた。
「美味い。これ、オレが持ってきたヤツだよな?」
「はい、いつも高級なお茶のお裾分けありがとうございます」
「気にするな。余ってるものだし。百足で飲むより雪菜に淹れてもらう方がいつも美味いからな」
ゆったりとしたティータイム。雪菜の膝の上では猫も気持ちよさそうに丸くなっていた。にゃおんともう一匹の猫が軀の側までやってきた。艶々した毛の黒猫。どうしたものかと軀が考えている間にその猫は膝の上に飛び乗って寛ぐように丸くなった。
「おいおい、いきなり慣れ慣れしいヤツだなコイツ」
驚きの声をあげるも黒猫は気にもせず尻尾を大きくゆっくり振っていた。
「フフフ、軀さんの膝の上が気に入ったようですよ」
「前来た時は凄い威嚇されたような記憶があるんだがな」
「そういえばそうでしたね。後から兄が来て、軀の事を引っ掻いた奴はどれだ? って凄い剣幕で大変でしたよ」
「は? 飛影がきたのか? アイツ何やってるんだよ、まったく……」
そう言いながらも軀はどこか嬉しそうな顔をして、それを見た雪菜はさらにニコニコと微笑んだ。
「そういえば、もう一匹いただろう? 白いのは今日はいないのか?」
何気なく聞いた軀の問いで、雪菜の表情が曇る。
「あのこは……、もうおばあちゃん猫だったので少し前に亡くなりました」
「……そうだったか。悪いこと聞いたな」
「いえ、軀さんがいらしたタイミングでお話しなきゃとは思っていたんですが…… もう何回か経験してるけどやっぱり慣れませんね」
雪菜はせいいっぱい泣くのを堪えるように微笑んだ。
「人間の生は短いです。でも猫や小動物はもっと短い。最初は分からなかったんです。そんな短い命の動物を飼って愛でるということが…… でも最近なんとなく分かってきた気がします」
コロリと一粒の氷泪石が床に落ちて跳ねた。一つ二つ…… ポロポロとこぼれた涙が次々と氷泪石と
なり床へ落ちる。
「……ひとりじゃ寂しいから。たとえ短い期間でも一緒に過ごした記憶は思い出に残りますから。だ
から精一杯愛情をおくるんだと思うんです」
ニコリと笑って、最後の氷泪石がこぼれ落ちた。
「雪菜は強いな……」
床に散らばった氷泪石を拾いながら軀は呟く。
この涙が猫だけに向けられたものではない事を軀は知っていた。
「最近思うんだ。飛影は人間も喰わないのになんであんなに成長が著しいのかと……」
「……」
「もちろんオレら妖怪の中に人間を喰わないヤツがいるのは知っている。雪菜みたいな氷女も食わないしな」
話しながら拾いあげた氷泪石をそっと雪菜の掌に渡した。
「……でも時々怖くなる。生命を燃やしてるんじゃないかと……」
そこまで口にして軀は黙りこんでしまった。
掌の中の氷泪石を手近にあった小皿に移して雪菜は再び軀を見る。彼女は物憂げな表情でお茶を飲
んでいた。
──このヒトは泣けない……
強く美しい元三竦みである軀を目の前にして、雪菜はそんな事を思う。
流した涙が石になる事で想いが記憶となり自分の中で昇華出来る自分と違い、抱え込んで抱え込ん
で。長い時間生きていく事はさぞかし大変だろう。この可愛らしいヒトに自分が出来ることはなんなのだろう……
「軀さん」
凛とした声で雪菜は軀に声をかける。
「兄は大丈夫です。絶対に大丈夫」
晴れやかな笑顔でそう言うと、軀は眩しそうに目を細めて小さく微笑んだ。
*
そんなやり取りをして雪菜と別れたのが数時間前。すぐに魔界に帰る気分にはなれず、ふらふらと
人の気配がない方へと彷徨ってこんな山奥まで来てしまっていた。
(雪菜と話をして少し気は楽になったがな……)
心配だったのだ。
火を使役する妖怪は他の使い手の中でも身体に対する負担が大きいとされている。強力なエネル
ギー源として人間を喰うならまだ良いだろう。でも飛影は違う。人間を喰わない。そして成長が急過ぎる。それを補うならどうするか? 自ずとその回答に行き着いてしまった。
今回も怪我の完治前なのに手合わせをしろと言ってきた。しっかり休めと言っても聞きやしない。
だから軀は飛影から逃げるように人間界へやってきた。
弱い奴は嫌いだ。強くなっていく飛影を見るのは楽しい。
でも……
──居なくなるのはもっと嫌だ。
不意に良く知っている妖気の気配を感じた。そして次の瞬間、耳元でザクッと雪を踏む足音が響く。
「探したぞ」
満天の星に黒い人影が割り込んできた。
「星が見えない」
そう軀が呟けば、黒いそれは小さく舌打ちをして邪魔にならないよう仰向けになっている軀の横に腰を下ろした。
「思ったより早かったな。見つけるのが上手くなった」
「フン、ご丁寧に雪菜に言伝(ことづて)していた癖によくいいやがる」
座った人影──飛影に話しかければ悪態が返ってきた。
いつもどおりのやり取り。平和そのものだ。
「飛影、知ってるか? あの星の輝きはオレが生まれる前の光らしいぞ」
そう言われ飛影も夜空を見上げた。が、軀が言っていることがイマイチ分からないようで小首を傾げていた。
そんな様子を見ながら軀はクスリと笑って説明を続ける。
「凄く遠くにあるんだ。光の速さで何万年、何億年かかるくらいの距離だ。そのぐらいの時間をかけて星の光がこの人間界に届く。既に存在しない星の光を見ているのかもしれないって訳だ。人間界は面白いな。短い命の生き物が住む世界と思っていたが、少し羨ましくなる」
再び空を見上げて軀は星を眺めていた。軀につられて飛影も空を眺める。確かに星空は魔界では見られないものだ。
二人で星空を眺める。濃紺の空に数えきれない星達。
空の片隅で一つの星がさぁっと流れた。
「今の見たか?」
「あぁ」
「あれが流れ星というやつか。初めて見たな」
興奮を隠しきれない様子で軀は話す。子供のように無邪気に振る舞う姿を飛影は目を細めて見ていた。
「……そろそろ帰るぞ」
ぶっきらぼうに言いながら、仰向けになっている軀に手を差し伸べた。
「また見れるかな?」
そう小さく呟いて軀は飛影の手をとる。
すっかり冷えてしまっている軀の手に一瞬不機嫌になりながらも、ぎゅっと手に力を込めて引っ張り起こす。
「好きなだけ見ればいい」
そう飛影は呟いて、二人は青白い雪原の中心で向かい合った。
「……オレはお前と見たいんだが、付き合ってくれるのか?」
悪戯っぽい笑みを浮かべながら尋ねれば、飛影が少し驚いて、そんな姿を見て軀はクスクスと笑いだす。
好きなだけ星空を見よう。
星に比べたら妖怪も人間もちっぽけな輝きだけれど。
二人で一緒に巡れれば、それはきっと幸せで──
握りしめたままの手がじんわりと温かくなる。
「あったかいな」
「お前が冷えすぎだ」
「そうか?」
「髪も濡れてるし、顔も冷たい……」
軀の頬に飛影の手がそっと触れる。その心地よい熱に思わず軀はうっとりとして目を閉じた。
そうして、それが合図のように二人の唇が重なる。
冷たいと温かいが混ざる感覚。
互いにその感覚に酔いしれて、数回触れあった唇は名残惜しそうにゆっくりと離れた。
二人から白い吐息が漏れる。
ぎゅうと強く抱きしめあって、冷たい空気の中でお互いの体温をかみしめた。
「……そろそろ帰るか」
ぼそりと軀が言えば、飛影はようやくその気になったかと安堵のため息をつく。
「一番近い魔界へのゲートは?」
「ここから北、40キロ」
「そうか。じゃあ早く百足に帰ろうぜ。あ、帰っても手合わせはしないからな。ここの怪我がきちんと治ってからだ」
飛影の右の肋骨あたりを指差して軀はニヤリと笑う。飛影は舌打ちをして、そっぽを向きながらも小さくコクンと頷いた。
星空の下、二人は雪原を駆けだした。
生きるべき場所である魔界へと。
二人一緒に帰っていく。
<<了>>